コラム
【速報⑦(パブコメ№137~189)】令和7年8月28日公表 「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表について を読む
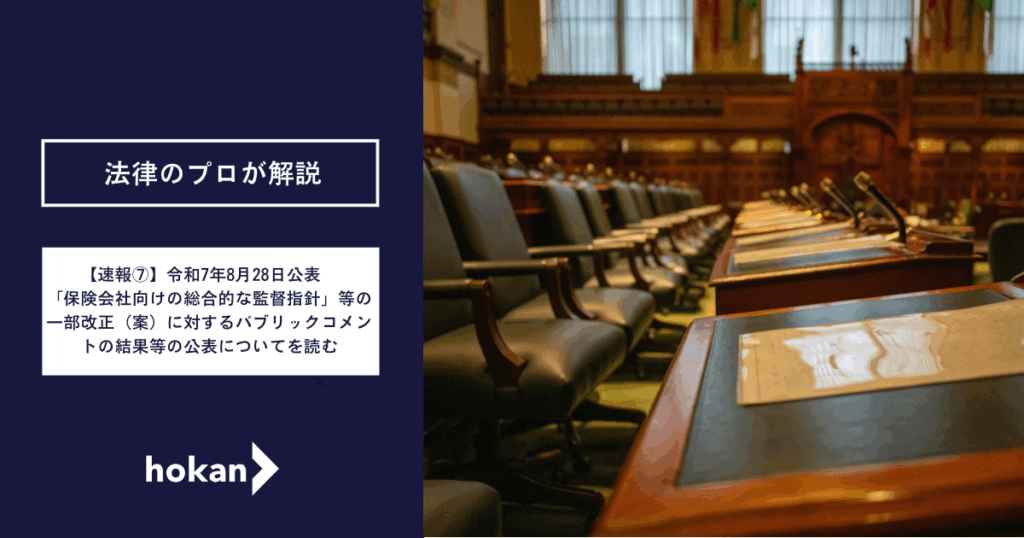
8 Ⅱ-4-2-12 部分④ (1)② 過度の便宜供与に係る判断基準 (イ(エ)(オ))(№137~189)
② 過度の便宜供与に係る判断基準
保険会社が保険代理店等に対して行う便宜供与に関し、過度なものであるか否かについては、以下に基づき判断する。
ア. 自社の保険商品の優先的な取扱いを誘引する便宜供与保険代理店等に対する便宜供与のうち、以下のいずれかの要素を含むものについては、特に顧客の適切な商品選択の機会を阻害するおそれが高いことから、過度の便宜供与に該当する。
(ア) 便宜供与の実績に応じて、当該保険代理店や保険募集人である保険代理店の役員又は使用人において保険契約数や保険引受シェアの調整が行われる場合
(イ) 保険代理店等から保険会社に対し、物品等の販売数量の目標設定や購入数量の割当て等が行われる場合
イ. 実質的に自社の保険商品の優先的な取扱いを誘引するもの
上記ア.のほか、保険代理店等に対する便宜供与が過度なものであるか否かについては、当該便宜供与の趣旨・目的のほか、価格・数量・頻度・期間及びその負担者等を総合的に勘案しつつ、当該便宜供与によって生じ得る弊害の内容・程度を考慮し、社会通念に照らして妥当であるかによって判断する。
なお、判断は個別具体的に行われるべきであるが、例えば、以下の行為については、実質的に自社の保険商品の優先的な取扱いを誘引するものとして、過度の便宜供与に該当し得る。
(エ) 本来は保険代理店等が負担すべき費用を保険会社が負担する行為、又は保険代理店等が自らの責任において行うべき業務に対し保険会社が役務を提供する行為
(オ) 保険代理店等の求めに応じ、役務の対価としての実態がない又は保険会社若しくは保険代理店等において対価性の検証が困難な業務委託費、協賛金、商標使用料、広告費用等の金銭を拠出する行為
(1)特に(エ)の本来は保険代理店等が負担すべき費用、保険代理店等が自らの責任において行うべき業務について質問がなされています。
№137
Q.「本来は保険代理店等が負担すべき費用」に関して、特定の保険代理店が独断によるシステム開発を行うものではなく、代理店と保険会社間でシステム上必要となる連携をするための費用など、保険会社の都合によるシステム開発・運用費用については、社会通念に照らして妥当な範囲で保険会社が相応の負担をすることは、過度の便宜供与に該当しないとの判断でよいか。
A.システム開発費用については、「本来は保険代理店等が負担すべき費用」や「保険代理店等が自らの責任において行うべき業務」に該当しないか、実質的な実施主体や開発の経緯・目的等の事情を、個別具体的に検討する必要があります。また、保険代理店と保険会社間でシステム上必要となる連携をするための費用についても、顧客の適切な商品選択の機会が阻害されていないか、Ⅱ-4-2-12 に沿って確認する必要があると考えます。
システム開発費用の検討に当たっては、「実質的な実施主体や開発の経緯・目的等の事情」を個別具体的に検討することとなりました。
№138
Q.保険会社は保険募集人に対する教育・管理・指導を行う責任を負っているため、保険会社が保険募集人(登録又は届出された個々の募集人を含む。)に対する教育・管理・指導を行うことは、保険代理店等に対する過度の便宜供与を理由に妨げられることはないという理解でよいか。
A.保険会社は、保険募集に関する法令等の遵守、保険契約に関する知識、内部事務管理態勢の整備等について、保険募集人に対する適切な教育・管理・指導を行う必要があります。一方で、保険業法第 294 条の3は、保険募集人に対して体制整備義務を課しており、保険募集人は、保険募集に従事する役員又は使用人に対して、適切な教育・管理・指導を行うことを求めています。
したがって、保険会社による保険募集人(保険募集に従事する役員又は使用人を含む)に対する教育・管理・指導についても、その態様によっては「保険代理店等が自らの責任において行うべき業務に対し保険会社が役務を提供する行為」等として、過度の便宜供与に該当し得ることから、Ⅱ-4-2-12(1)②に照らして判断する必要があると考えます。
保険代理店への教育・管理・指導の名目でも、過度の便宜供与に当たり得るものを実質的に判断することが明記されました(№151参照)。
№139
Q.保険会社と保険代理店において、顧客に対し、保険商品の保険募集およびアフターフォローを分担して対応するケースにおいて、保険会社がその分担している業務の内容に応じて、一定の費用の負担や役務の提供を実施することは、保険会社や保険代理店の事業活動として自由であり、防止すべき「過度の」便宜供与には該当しないものと考えているが、その考え方に相違ないか。
A.「保険会社と保険代理店の分担」については、一概に否定されるものではありませんが、保険会社が費用を負担又は役務を提供する場合には、当該費用負担や役務提供の内容が、本来は保険代理店が負担すべき費用又は行うべき業務でないかを、代理店業務委託契約の内容、他の保険代理店への費用負担や役務提供の状況のほか、保険会社による費用負担や役務提供の代理店手数料への反映状況等を踏まえ、慎重に検討する必要があると考えます。
「本来は保険代理店が負担すべき費用又は行うべき業務でないか」は、「代理店業務委託契約の内容、他の保険代理店への費用負担や役務提供の状況のほか、保険会社による費用負担や役務提供の代理店手数料への反映状況等を踏まえ」、慎重に検討することとされました。これは保険代理店ごとに個性に応じて費用負担や役務提供の内容を個別交渉で決めるにあたって、他の代理店の契約条件などとの比較が求められるということ、また、費用負担をした場合代理店手数料への反映を検討することが求められることになりそうです(№143、149同旨)
なお、№154、168の事例は、本来は保険代理店等が負担すべき費用、保険代理店等が自らの責任において行うべき業務に該当するおそれが高いとされています。
〇№154の例
【以下の費用の全部又は一部を負担する行為】
・保険代理店が主催するイベントの開催費用
・保険代理店が受ける経営コンサルティング費用
・保険代理店に所属する保険募集人向けの研修会(保険会社が実施する研修会を除く)のうち、保険代理店が自ら実施するものに関する費用
・保険代理店が募集関連行為従事者に支払う手数料
・保険代理店の広告・キャンペーン費用
・保険代理店の募集に関する費用(保険代理店の営業目的での契約者へのダイレクトメール・電話に関する費用等)
・保険代理店が本来作成するべき募集資料の作成費用
・保険代理店が、取扱う保険商品を決定する際に、当該保険代理店自身の定め等により、保険会社と代理店以外の第三者による保険商品の評価サービスを受けることを必要としている場合に、当該評価サービスを受けるために第三者に支払う費用【以下の役務・物品を提供する行為 】
・保険代理店に所属する保険募集人の採用支援(保険募集人候補の紹介等)
・保険代理店がキャンペーンで使用する景品の提供
・保険代理店の紹介動画の作成
・保険代理店の店舗開設の支援〇№168の例
・既契約者からの追加契約を念頭に、代理店がDM一斉送付を行う際の、印刷費や郵送費を保険会社が負担する行為
・保険会社自身によるものであるが、特定の代理店の顧客だけのためにDMを送付する行為(1の潜脱行為)
・代理店が集客したセミナーに保険会社が無償または格安で講師派遣、あるいは実費用の一部負担をする行為
・保険会社自身が実施するセミナーであるが、特定の代理店の顧客を対象とする行為(3の潜脱行為)
・特定の代理店の顧客を対象とするが、代理店、保険会社が共同でセミナー開催すること(3、4の潜脱行為)
№142
Q.Ⅱ-4-2-12 (1)②イ. (エ)の 「保険代理店等が負担すべき費用」「保険代理店等が自らの責任において行うべき業務」については、保険会社と保険代理店の間で交わされている約定・規則等の条件が異なれば、必ずしも同一の判断となるものではない一方で、前提となる条件が同一であれば、判断基準・結果も同一となるという理解でよいか。
A.個別具体的に判断をする必要がありますが、保険会社と保険代理店の間で交わされている約定・規則等の条件が異なれば、必ずしも同一の判断となるものではないと考えます。
一方で、約定・規則等の条件が同一であったとしても、支出対象となる項目、提供する役務の内容・程度等に応じて、個別具体的に判断する必要があるところ、必ずしも判断基準・結果が同一となるものではないものと考えます。なお、保険会社と保険代理店の間で約定すれば、当該約定に従った費用・業務負担が過度の便宜供与に該当しないこととなるものではなく、個別具体的に判断する必要があると考えます。
これは一度検討した条件と同一のものであっても、「支出対象となる項目、提供する役務の内容・程度等に応じて、個別具体的に判断する必要がある」として、一案件ごとに代理店等が負担すべき業務か否か判断を行うことを求めているように読めます。また、「保険会社と保険代理店の間で約定すれば、当該約定に従った費用・業務負担が過度の便宜供与に該当しないこととなるものではなく」として、契約内容では「代理店が負担すべき費用」「代理店等が自らの責任で行うべき業務」に当たるか否かは一義的に定まらないと解されます。判断要素としては№139、143(「代理店業務委託契約の内容、他の保険代理店への費用負担や役務提供の状況のほか、保険会社による費用負担や役務提供の代理店手数料への反映状況等)が参考になります。
№147
Q.Ⅱ-4-2-12 (1)②イ. (エ)に関して、本来は保険代理店等において対応すべきお客様からの問合せが保険会社のコールセンター等に入り、そのままコールセンター等で対応することは、「保険代理店等が自らの責任において行うべき業務に対し保険会社が役務を提供する行為」に該当する可能性はあるものの、お客様の利便等の観点から行うものであり、直ちに問題になるものではないという理解でよいか。
A. 個別具体的に判断をする必要がありますが、例えば特定の保険代理店についてのみ、コールセンター業務を事実上代替する形で、保険会社が対応を行うような場合には、過度の便宜供与に該当するおそれが高いものと考えます。
この例は、特定の保険代理店についてのみ対応を代行するという限定的な場合について回答がなされたものと解されます。
№150
Q.Ⅱ-4-2-12 (1)②イ. (エ)に関して、保険代理店の役員または使用人に対する教育・管理・指導は、保険代理店が主体的に行うことに加えて、保険募集人が公正な保険募集を行うための育成や資質向上の観点から、保険会社としても行うべきものと認識している。
保険会社が行う保険代理店の役員または使用人に対する教育・管理・指導は、本来保険代理店が担うべきものを代替するなどの保険代理店への便宜供与として機能することがないよう、必要最低限かつ合理的で対外的にも説明可能なものであるべきという理解でよいか。
その場合、保険会社による保険代理店に対する以下の支援は、顧客の適切な商品選択の機会が阻害されるおそれがない前提において、直ちに「保険代理店等が自らの責任において行うべき業務に対し保険会社が役務を提供する行為」には該当しないという理解でよいか。
・保険募集人の育成を目的に、広くすべての保険代理店(または一定の合理的な基準等に基づき選定する保険代理店)の募集人を対象として、教育コンテンツを提供すること
・保険会社が保険代理店の役員・使用人の支援を直接行うことに合理性があるもの(例えば、商品改定の趣旨・背景に関する保険代理店向けの勉強会など、一般的に保険代理店が単独で実施することが困難であるものなど)
・保険代理店内での「教育・指導」に関する体制が整うまでの間、適正な募集管理態勢の構築を目的として、反復・継続的にならない範囲で、必要最小限かつ合理的な期間に限定したうえで、保険代理店が自ら実施することが困難な業務の支援を行うこと一方で、上記に該当せず、保険代理店が行うべき業務を保険会社が無償で代行・支援(保険代理店の自立化を阻害し得る同行支援を含むが、保険会社の専門的な知識等を用いた補完的説明を要するような同行支援は除く)する、保険会社が特定の保険代理店の求めに応じて当該保険代理店の使用人に対する教育を反復・継続的に担う、あるいは保険代理店の主体的な関与がないまま保険会社が当該保険代理店の使用人に対する教育・指導を肩代わりするなどの行為は、「保険代理店等が自らの責任において行うべき業務に対し保険会社が役務を提供する行為」に該当し得るという理解でよいか。
A.保険会社は、保険募集に関する法令等の遵守、保険契約に関する知識、内部事務管理態勢の整備等について、保険募集人に対する適切な教育・管理・指導を行う必要がありますが、教育・管理・指導についても、その態様によっては「保険代理店等が自らの責任において行うべき業務に対し保険会社が役務を提供する行為」
等として、過度の便宜供与に該当し得ることから、Ⅱ-4-2-12②に照らして判断する必要があると考えます。なお、保険代理店が行うべき業務に対して保険会社が無償で役務を提供する行為は、「保険代理店等が自らの責任において行うべき業務に対し保険会社が役務を提供する行為」に該当するおそれが高いことを踏まえ、顧客の適切な商品選択の機会を阻害するものでないか、慎重に判断・検証する必要があると考えます。御指摘のような同行支援についても、取り扱う保険商品の特性等も踏まえつつ、上記に照らしてその適否について判断される必要があると考えます。
また、保険業法 294 条の 3 は保険募集人に対して体制整備義務を課しており、保険募集人は、保険募集に従事する役員又は使用人に対して、適切な教育・管理・指導を行うことを求めています。したがって、保険会社が、保険代理店において保険募集に従事する役員又は使用人に対する教育を反復・継続的に担うことや、保険代理店の主体的な関与がないまま教育・指導を肩代わりすることも、「保険代理店等が自らの責任において行うべき業務に対し保険会社が役務を提供する行為」に該当するおそれが高いことを踏まえ、顧客の適切な商品選択の機会を阻害するものでないかという観点から、慎重に判断・検証する必要があると考えます。
保険会社が、保険代理店において保険募集に従事する役員又は使用人に対する教育を反復・継続的に担うことや、保険代理店の主体的な関与がないまま教育・指導を肩代わりすることは、「保険代理店等が自らの責任において行うべき業務に対し保険会社が役務を提供する行為」に該当するおそれが高いとされました。
№153
Q.「本来は保険代理店等が負担すべき費用を保険会社が負担する行為」について、汎用的な保険募集システムであっても、特定の保険代理店向けの付加サービスを提供するための一部機能(申込フォーム上の入力補助をする機能等)を追加開発する場合は、その開発費用は保険代理店等が負担すべきであるという理解でよいか。その場合、保険会社から保険代理店に支払う手数料率を削減するまたは代理店に費用請求する等の対応をすれば、保険会社が一時的に開発費を負担した場合でも実質的に保険代理店が負担していると見做せ、便宜供与には該当しないか。なお、手数料率の削減については、システム開発により代理店側のロードが削減され、従来の役務(代理店の業務)が縮小するため、その役務に対する対価(手数料)を削減するという考え方を想定している。
A.個別具体的に判断する必要がありますが、御指摘のようなケースは、保険会社による費用負担が、適切に代理店手数料や保険代理店の費用負担に反映されている限りにおいては、直ちに過度の便宜供与に該当するものではないと考えます。ただし、代理店手数料に適切に反映されているかは、判断が難しいことを踏まえ、顧客の適切な商品選択の機会を阻害するものでないか、慎重に検討をする必要があると考えます。
代理店手数料とシステム開発費用の関係性の説明の一例として、「手数料率の削減については、システム開発により代理店側のロードが削減され、従来の役務(代理店の業務)が縮小するため、その役務に対する対価(手数料)を削減する」というものがあり得ることを示したものと解されます。
№167
Q.乗合保険代理店が主催する顧客向けセミナー(保険商品に関する説明を行わないセミナー)において保険会社の従業員が講師を務めることは、当該保険会社と当該保険代理店が協働して顧客に対する情報提供を充実させるために行うものであり、そのセミナーに続けて当該保険会社の保険商品のみの案内を行わず、顧客の適切な商品選択の機会が確保される限り、過度の便宜供与に該当しないという理解でよいか。
A. 過度の便宜供与に該当し得るかは、当該便宜供与の趣旨・目的のほか、価格・数量・頻度・期間及びその負担者等を総合的に勘案しつつ、当該便宜供与によって生じ得る弊害の内容・程度を考慮し、社会通念に照らして妥当であるかによって判断される必要があり、一概に回答することは困難です。なお、今般の監督指針改正は、保険会社から保険代理店等に対する便宜供与が過度なものとなっていないか、Ⅱ-4-2-12(1)②に掲げる判断基準に照らして判断するとともに、顧客の適切な商品選択の機会が阻害されていないかについて、内部監査や取締役会等における評価・対応の検討を行うとともに、顧客の適切な商品選択の機会が阻害されていると認められる場合には、適切な措置を講じること等を求めるものです。このため、セミナーにおいて保険商品の説明を行うか否かといった外形的な要因のみならず、先に述べたような要素に照らして、顧客の適切な商品選択の機会を阻害するものでないかを検討する必要があると考えます。
これは乗合代理店における顧客向けセミナー(保険商品に関する説明を行わないセミナー)については、代理店が行う業務か否か等については触れず、セミナーにおいて保険商品の説明を行うか否かといった外形的な要因のみならず、先に述べたような要素(当該便宜供与の趣旨・目的のほか、価格・数量・頻度・期間及びその負担者等を総合的に勘案しつつ、当該便宜供与によって生じ得る弊害の内容・程度を考慮し、社会通念に照らして妥当であるか)に照らして、顧客の適切な商品選択の機会を阻害するものでないかを検討する必要があるとされました。
(2)(オ) 保険代理店等の求めに応じ、役務の対価としての実態がない又は保険会社若しくは保険代理店等において対価性の検証が困難な業務委託費、協賛金、商標使用料、広告費用等の金銭を拠出する行為
№163
Q.広告・宣伝の類は、事前に効果を測りがたく、対価の適切性に関する判断が難しいと考えられるが、類似の取引事例などから価格について相当である旨の判断を行ったものや公正な入札などで決定されたものなどは、問題ないと考えてよいか。
A.対価の適切性の判断にあたっては、御指摘のように、類似の取引事例などから価格の相当性を推定する方法、又は公正な入札などにより決定する方法が考えられますが、特定の方法が適切であるか否かについては、個別具体的な判断が必要であると考えます。
対価の適切性の判断として、何をもって類似の取引といえるかはについては保険会社内でも検討が必要と思われます。
▼【速報⑧】令和7年8月28日公表 「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表について を読む
https://hkn.jp/column/50
執筆者プロフィール

- 株式会社Hokanグループ 弁護士/パブリック・アフェアーズ室長
兼コンプライアンス室長
2008年慶應義塾大学法科大学院卒業、2009年弁護士登録(東京弁護士会)。都内法律事務所・損害保険会社・銀行を経て、株式会社hokanに入社。平成26年保険業法改正時には、保険会社内で改正対応業務に従事した経験を持つ。「「誠実義務」が求める保険実務におけるDXの方向性(週刊金融財政事情 2024.9.17)」、「実務担当者のための今日から始める保険業法改正対応」(保険毎日新聞 2025.5.15~7.3)等を執筆。
関連記事
- 2025年8月18日令和7年6月分「業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点」を読む
- 2025年8月1日参議院常任委員会調査室・特別調査室「令和7年保険業法改正の国会論議」を読む
- 2025年8月1日登壇レポート:保険業法改正と業務負荷をチャンスに変える経営戦略@大阪
- 2025年7月29日代理店業務品質評議会(第1回)議事概要を読む
執筆者監修のお役立ち資料
・2025年監督指針徹底解説 保険代理店の今からできる対応事項book
・金融庁出向経験弁護士が答える 「保険業法改正Q&A一問一答」
・【ハ方式→ロ方式】意向把握 完全移行マニュアル
・弁護士監修 乗合代理店の為の保険業法改正対応の手引き
hokan®︎の資料はこちら!
