コラム
【速報⑩(パブコメ№355~385)】令和7年8月28日公表 「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表について を読む
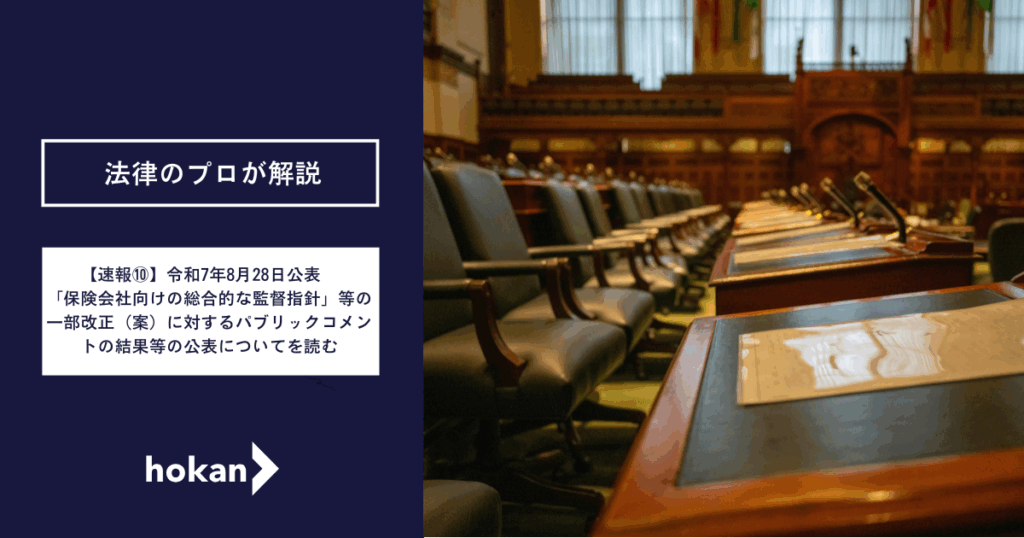
11 Ⅱ-4-5 部分(№355~363)
Ⅱ-4-5-2 主な着眼点
(1) 顧客等に関する情報管理態勢
① 経営陣は、顧客等に関する情報へのアクセス及びその利用は業務遂行上の必要性のある役職員に限定されるべきという原則(以下「Need to Know 原則」という。)を踏まえ、顧客等に関する情報管理の適切性を確保する必要性及び重要性を認識し、業務の内容・規模等に応じて、そのための組織体制の確立(部門間における適切な牽制の確保を含む。)、社内規程の策定、金融グループ内の他の金融機関(持株会社を含む。)との連携等、内部管理態勢の整備を図っているか。② 顧客等に関する情報の取扱いについて、具体的な取扱基準を定めた上で、研修等により役職員に周知徹底しているか。特に、当該情報の他者への伝達については、上記の法令、保護法ガイドライン、金融分野ガイドライン、実務指針の規定等に従い手続きが行われるよう十分な検討を行った上で取扱基準を定めているか。
③ 顧客等に関する情報へのアクセス管理の徹底(アクセス権限を有する者の範囲が Need to Know 原則を逸脱したものとなることやアクセス権限を付与された本人以外が使用することの防止等)、内部関係者による顧客等に関する情報の持出しの防止に係る対策、外部からの不正アクセスの防御等情報管理システムの堅牢化などの対策を含め、顧客等に関する情報を適切に管理するための態勢が構築されており、コンプライアンス部門の関与のもと当該顧客等に関する情報の管理状況を適時・適切に検証できる体制となっているか。また、特定職員に集中する権限等の分散や、幅広い権限等を有する職員への管理・牽制の強化を図る等、顧客等に関する情報を利用した不正行為を防止するための適切な措置を図っているか。
- 「(1) 顧客等に関する情報管理態勢」①~③の名宛人は保険会社だが、、監督指針Ⅱ-4-2-9(2)のとおり、保険募集人の規模や業務特性に応じて、保険募集人に準用されている。(№355)
- Ⅱ-4-5-2(1)①に関して、Need to Know 原則は、主要行等向けの監督指針や金融商品取引業者等向けの監督指針で規定されているものと同一であり、その具体的な内容や考え方については、令和 4 年 4 月 22 日付で貴庁が公表している「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」の内容が当てはまるが、一連の事案を踏まえれば、Need to Know 原則における「業務遂行上の必要性」については、個人情報保護法のほか、独占禁止法や不正競争防止法等に抵触するおそれがないか、といった観点からも、当該情報へのアクセス及びその利用の必要性を適切に判断する必要がある(№356)。また、その必要性の判断には、個人情報保護法等の関係法令に照らして保険会社が判断すべきものですが、外部専門家の活用等も有効である(№357)
12 Ⅱ-4-12部分(№364~385)
Ⅱ-4-12 政策保有株式の縮減
(1) 意義
損害保険業界においては、企業向け保険契約の入札等において、いわゆる政策保有株式等の実績が少なからずシェアに影響を及ぼしており、適正な競争を阻害していた。その結果、保険商品や保険サービス自体で適正に競争を行うよりも、保険料水準やシェアを維持するため、競争を避け、事前に保険料等を調整するといった不適切事案が発生し、業界に対する信頼が大きく損なわれた事例が認められている。
このように、保険市場においては、政策保有株式が公正な競争を阻害する要因となり得ることを踏まえ、保険会社は以下の点を重視して、コンプライアンス上問題となり得る行為を防止する態勢を構築すべきである。
なお、政策保有株式のほか、保険シェアを獲得することを意図した預金協力や融資も、政策保有株式と同様に、公正な競争を阻害する要因となり得ることにも留意する。(2) 主な着眼点
① 保険会社は、政策保有株式(非上場株式を含む)について、早期に縮減する方針を定めているか。特に、上場株式については、明確な年限を定めて縮減する方針を定めているか。
② 実質的な政策保有株式の保有継続につながらないよう、純投資と政策保有の区分の考え方、業務資本提携に付随した出資等について、企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)等を踏まえ、開示や関係者への説明等の十分な対応を行っているか。(注) 政策保有株式は、業務資本提携に付随した出資の場合等、一律にその保有が否定されるものではないが、その保有の合理性を投資者等が判断できるよう、開示等を行うことが重要である。
- 健全かつ適切な業務運営の確保は、生命保険会社・損害保険会社を問わず求められるものであることから、生命保険会社を含め、保険会社に対して政策保有株式を早期に縮減する方針を定めるよう求めている(№371)
- 純投資と政策保有株式の区分の基準については、企業内容等の開示に関する内閣府令のほか、企業内容等開示ガイドラインを踏まえ、各保険会社において検討されるべき(№376)、であり、企業内容等開示ガイドラインにおいて、「純投資目的」とは、「専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とすることをいう。」とされているため、営業関係強化の目的を有することを以て直ちに純投資に該当しないとまではいえない。一方で、同ガイドラインにおいては「当該株式の発行者等が提出会社の株式を保有する関係にあること、当該株式の売却に関して発行者の応諾を要すること等により、発行者との関係において提出会社による売却を妨げる事情が存在する株式は、純投資目的で保有しているものとはいえない」とされていることも踏まえ、発行者等との関係性までを確認した上で、純投資として区分することが適切かを検討する必要がある(№377)
▼【速報⑪】令和7年8月28日公表 「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表について を読む
https://hkn.jp/column/53
執筆者プロフィール

- 株式会社Hokanグループ 弁護士/パブリック・アフェアーズ室長
兼コンプライアンス室長
2008年慶應義塾大学法科大学院卒業、2009年弁護士登録(東京弁護士会)。都内法律事務所・損害保険会社・銀行を経て、株式会社hokanに入社。平成26年保険業法改正時には、保険会社内で改正対応業務に従事した経験を持つ。「「誠実義務」が求める保険実務におけるDXの方向性(週刊金融財政事情 2024.9.17)」、「実務担当者のための今日から始める保険業法改正対応」(保険毎日新聞 2025.5.15~7.3)等を執筆。
関連記事
- 2025年8月18日令和7年6月分「業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点」を読む
- 2025年8月1日参議院常任委員会調査室・特別調査室「令和7年保険業法改正の国会論議」を読む
- 2025年8月1日登壇レポート:保険業法改正と業務負荷をチャンスに変える経営戦略@大阪
- 2025年7月29日代理店業務品質評議会(第1回)議事概要を読む
執筆者監修のお役立ち資料
・2025年監督指針徹底解説 保険代理店の今からできる対応事項book
・金融庁出向経験弁護士が答える 「保険業法改正Q&A一問一答」
・【ハ方式→ロ方式】意向把握 完全移行マニュアル
・弁護士監修 乗合代理店の為の保険業法改正対応の手引き
hokan®︎の資料はこちら!
